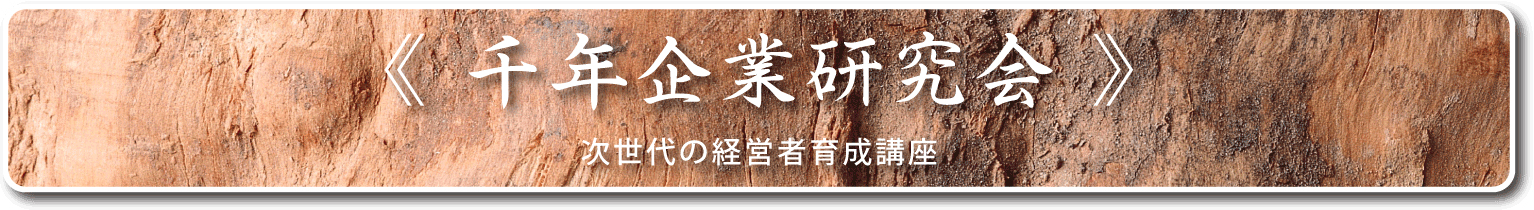
第129回 千年企業研究会(福井塾)議事録
令和6年5月21日
法人税について(概論)
これまでのアート引越センターの話は卒業しまして、今日から法人税の講義となる訳ですが、しっかり中身まで掘り下げると 4、5年掛かってしまうと思います。そこで、ここでは法人税が実際に幾ら掛かるかといった実務よりも本質の理解に重点をおいて講義していきます。本日は大学で講義が始まる際にオリエンテーションを行いますが、その様なイメージで進めていきたいと思います。
いつもお伝えしている事で、繰り返しになってしまいますが、大前提として、この場では皆さんが経営者になった時にどういう知識が必要かという事について、私の経験や私なりの考えを基にお伝えしております。経営者にとっては、色々な知識が必要なのですが、法人税に関する知識も必要で重要なのです。
法人税とは何かというと、ひと言で言えば、「法人の所得税」です。法人の所得に対して、ある一定税率を掛けて税率を算出し、それを納めるのが法人税です。では、「法人の所得とは何か?」という事になるかと思います。因みに皆さんの様な会社員は給与所得を得ており、源泉徴収されている方が殆どですので、会社が月々の給与から天引きし、年末には年末調整を行い、所得税の算出と納付を行っているので、所得税の事を知らなくても個人の所得税を納めているのです。一般的に法人税は法人の所得に対する税金、所得税は個人の所得に対する税金という様に認識して良いかと思います。
前職での経験もあり、その時々に感じた事等を踏まえ、私が法人税について、特にお伝えしたい 3点をお話したいと思います。
法人税についての書籍か何かで読んだものだったと思いますが、一番印象に残っているのが、アメリカ人の経営者の多くが法人税を勉強しているという事です。企業経営においては多くのコストが掛かってきます。給与、商品の仕入れ、電気代、ガス代等、数え上げていったら、キリがない。その中で最大のコストは何かというと、税金だって言うんです。アメリカ人は最大のコストは税金だと。
だから法人税を勉強して節税に努める事は、コスト削減に繋がるのです。法人税を勉強する事は実利がある訳です。逆に知らないで何か手続きをしてしまい、これに対して多額の税金が掛かってしまう、といったケースもあります。そういう事を経営者たる者、知っていないといけない。だから節税に努める、そこまではいいんですが、お伝えしたいのはそこから一つ先なんです。節税はやらなきゃいけない、無駄な税金を払う必要はないのだけど、脱税はやってはいけない。うまくやれば節税になるけど、足を踏み外してアウトって言われたら脱税になってしまう。脱税っていうのは罪ですから、刑事・民事両方問われます、脱税は国民としての恥なんです。絶対にやってはいけないという事をしっかり認識頂ければと思います。この事が 1番目に申し上げたい事です。
脱税なんかする訳ないという皆さん方、給与所得者という立場から言うと、脱税のしようがないんです。サラリーマンは 10割方所得を把握されている。商人は 5割、税務署から見て、5割は把握出来ないそうです。農業だと 3割しかない。私含め、皆さん方サラリーマンですから源泉徴収されている人は脱税のしようがないんです。経営者になると、これが法人税に絡んできますから難しい訳ですが、絶対に足を踏み外さない事、これを忘れないで頂きたいと思います。
2番目に法人税の本質を理解する為に、何故そうなっているのかという成り立ちについて学ぶ事でより理解を深めて頂きたいと思います。
法人税の細かな内容については、コロコロ変わります。具体的に言えば、1年に1回変わります。これは国会で税制改正を行うからです。それは何故かというと。政策や経済の流れから税金を緩めよう、引締めようだとか、貧困層に対してもっと非課税額を引き上げていくといった、いろんな観点から時の流れに伴って税制は変化していくからです。
一つ例を挙げると、企業が損失を出す、要するに赤字になると損失額として計上されます。翌期もまた赤字だったら損失が出る、この損失額はどんどん累積出来るんです。それで累積していって、今期は利益が出た、じゃあ利益が出たから税金を払うのかというとそうじゃないんです。過去累積損失、累損って言いますが、例えば、累損が50億円ある企業が今期10億円の利益が出たとします。何も知らなければ、今期の10億円に対する法人税を納める事になりますが、この「前期までの累積損失を今期に繰り越せる。」という事を知っていると、今期の利益を含めても累積損失が40億円なので、今期も法人税が0で済むという判断が出来ることになります。
何故、企業がこの様になったかというと、事の発端はあるヨーロッパの国、スペインだかオランダで船を作って、外国へ行き、そこの産物をたくさん船に積み込み持って帰り、自国で売りさばく。珍しいものですから 10倍 20倍の高値で売れる、そうすると莫大な利益が出ます。が、他所の国へ行くには結構な船が必要となる、そこで初めてこういう事業で儲かるから投資してくれる人いませんかと募る。これが株式の始まりだと言われています。投資により無事に船が造れて、国外へ渡り珍しい物を仕入れ自国で売り、出た儲けを投資額に応じて配分しました。それは期間として 3年分にもなったりする為、途中では儲けは出ていないので、もちろん赤字となる、2年目もそう、でも3年目で大きく黒字になったりする。だから累積損失というもので勘案してあげる、企業はゴーイングコンサーン「継続性の原則」という大前提があるものと考えられる様になりました。そういうものの考え方があることは理解して頂きたいと思います。
3番目に判断に迷ったら独断で絶対に決めない事です。独断で決めないという事は何かあったら税理士なり公認会計士なり、必ず相談する。社内でこうなったが、税務上この処置でいいのかと。するとこういう事はダメだよ、こういうふうにやりなさいと言ったアドバイスをしてくれる筈だからです。毎年の様に税法が変わるものだから付け焼刃の知識ではなく、プロの意見を聞く事が重要となります。以上の3点、これだけは絶対に皆さんにも覚えて頂きたいと思います。
【3つのポイント】
①脱税は絶対ダメ
②本質を理解する
③法人税の知識をしっかり身に着けた上で、専門家の意見も聞く
私も色々と法人税を勉強してきましたが、やはり絶対に忘れてはいけないというのは、今お話してきました3点だと思いますので、覚えておいて頂きたいと思います。これだけ覚えて頂ければ、本日のオリエンテーションは大成功といえます。
7.法人税と所得税の違い
それでは最初に法人税と所得税の違いについて触れたいと思います。簡単に言えば、法人の所得に対する税が法人税、個人の所得に対する税が所得税なのですが、勉強するにあたり、所得税は非常に難しく、法人税の方が易しいのです。ですから、本来は所得税を先に勉強する方が理解が早いのです。ただ、法人税を先に勉強しても特段支障はありません。
所得税の方が難しいというのは10個の所得に分かれているからです。
【所得の種類】
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得※元々は法人事業も含まれていた。
⇒所得税の事業所得と法人所得を分けた。
(現在は個人の事業所得のみ)
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得
元々は法人税なんてものはなく、所得税のみがあり、法人に対する所得税の一種として存在していましたが、明治中期に所得税法の改正により、法人に対する所得税が分離し法人税という形になりました。この様な法人税と所得税の関係を知っているか知らないかはとても重要なのです。
法人税が所得税から分離した事もあり、所得税法では定められているのに、法人税法では記載されていなかったり、決められていない事があります。ですが、それは法人税では無税、つまり税金を払わなくて良いという事ではなく、所得税法に立ち返らなければいけないという事なのです。この法人税の成り立ちを知らないと、払わなければならない税金を知らずに脱税してしまう危険性もある訳です。
次回から愈々法人税の各論に入っていく予定です。
以上