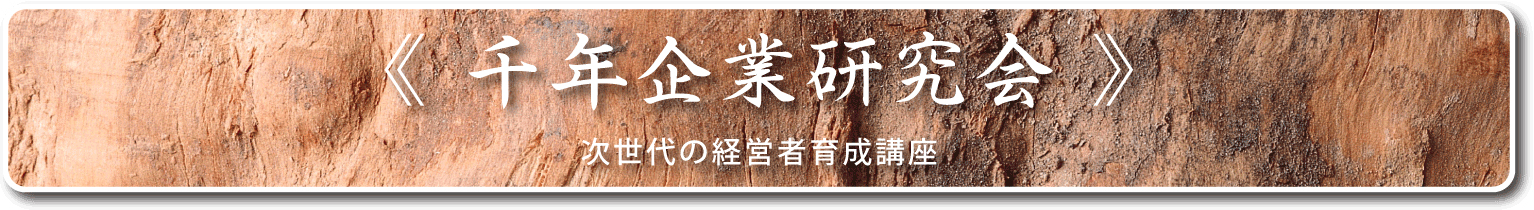
第134回 千年企業研究会(福井塾)議事録
令和6年12月17日
法人税について(4)
今年最後の勉強会を始めたいと思います。法人税を学んでいる訳ですが、遅々として進まないと感じているかもしれません。けれど、続けていく事で段々と理解が深まっていくものと思います。細かな事も話しておりますが、基本的な事が理解出来れば、それで充分です。本日もレジュメに沿って話していきたいと思います。
本法と措置法
本法というのは法人税法の事です。措置法というのは租税特別措置法、略して特措法とも言ったりします。法人税を学ぶ上で、何故、租税特別措置法も並行して学ばないといけないかというと、法人税というのは、所得税もそうですが、こうした大きな法は中々改正をしません。例えば、会社法等は、それこそ100年に一度とまではいきませんが、法律の所謂根幹を為すものは中々改正をしないのです。ではどの様にするかというと、措置法の様な細分化されたものを改正します。租税特別措置法という名前の通り租税に関するもの法人税・所得税・消費税等が一纏めに入っています。この様に法人税法の下に租税特別措置法があるという事を理解して頂きたいと思います。
何故この様な変更し易い法律を作っておいた方が良いかというと、税というのは「国会の立法なくして課税なし」と言われるからです。どういう事かというと、我々は納税者として、今年はこういう税金を取るぞと事前に知らせて頂けると良いのですが、税金が足りないから皆から幾ら徴収する、といきなり言われてもそんなのは有り得ません。我々が払う税金というのは国会の立法、つまり国会で議論して通過しない限り、新たな税金を納める事はあり得ないのです。これを租税法律主義と言います。この様な大前提があるから我々は安心して日頃生活が出来る訳です。
遥か昔の様に米が沢山取れたから多く納めろとか、西洋辺りでは酷い税金の取り立てが歴史にありました。そういった歴史を踏まえて、税金はその国の立法組織で論議されて決定しない限りは徴収しない。と、近代国家ではその様になっていった訳です。
租税法律主義を学ぶ上で覚えて頂きたいのが決まった法律で縛られていない「通達」です。この通達は国税庁長官から引っ切り無しに出ています。これに基本をつけた基本通達というものは行政庁内部の命令文書で、所轄の税務署員に対する統制となります。要するに、税務署署員に対して、こういう見解で税金を取り立てろというのが通達です。それは法律に基づいた見立てである筈で、法律に基づかない、法律を前提としない基本通達だけで税金を取るというのは有り得ません。この法律に基づいた基本通達が何故あるかというと、法人税があって、それから租税特別措置法があってとなると、細かいニュアンスで色々な解釈が出来てしまうのです。税務署員だけで何万人いるか分かりませんが、各々が勝手な解釈をしない為に、こういった通達が出されるのです。経理部や税理士、会計士も含めて、この基本通達を実務的に勉強する事が大事なのです。
一例で、アメリカで流行ったストックオプション、これが何かというと社員に賞与を配る時に、現金ではなく株を渡すものです。例えばAという人が会社に勤めていて、賞与で100万円を払う代わりに、株を5万株上げますと、これがストックオプションです。性質として、貰った株を現金に変えた時に、一時所得という扱いになりました。所得税を勉強しないとなかなか判らないと思いますが、不動産の家賃を得ている人の所得、それから事業の所得、給与所得、退職金所得から山林所得や、無形の何か売却した時に得る譲渡所得とか、宝くじに当たったなんていう一時取得、それから何処にも入らない雑所得、こういう分類があります。
話を戻して、ストックオプションで一時所得となると、要するに控除額が違ってくる訳です。給与所得控除と何が大きく違うかというと、一時所得で100万円手に入りました、これは滅多にある事じゃないから、担税力、つまり税金を納める力、それが劣後する訳です。有難い事に2分の1になります。税金の計算をすると100万円だったら50万円についてだけ課税すると、なおかつ控除額が5万円程度あり、45万円に税率を掛ける事で税金が計算される訳です。
ところが、ある時突然、通達が出ました。要するにストックオプションこれは給与所得じゃないかと。という事で、一時所得だったものが給与所得になった訳です。こういったストックオプションを使っている場合、非常に大きな金額となるケースが多い為、それが給与所得に加算されびっくりする様な税金が掛かってくる訳です。何か法律で国会でも通ったのか聞いた事もない、国会議員が論議した記憶もない、いきなり決まってしまって大論争となり、訴訟なんかも起きた様ですが、最終的には給与所得で変わらなかった様です。つまり何を言いたいかというと、多少ニュアンスは違うかもしれませんが、法律で決まっている以上に、この通達の威力が凄いという事を皆様方の記憶に留めておいて貰いたいのです。
少し脇道に逸れましたが、税に関しては毎年改定される訳です。これも社会常識として覚えて貰いたいのですが、各政党には税務調査会といって、税金を勉強したり、法律を決めたりする組織があります。一番有名なのは自民党の税務調査会です。なぜ有名かというと、自民党の税務調査会で今回こういうふうに法律改正しようとなった場合、自民党が多数を占めていた時は、それがそのまま通る訳です。だから自民党の税務調査会は何を考えているのかを皆さん非常に注目していました。ところが最近ですと、自民公明が過半数を割っている為に国民民主党の協力が必要となり、基礎控除と給与所得控除の合計額103万円を見直すという事で、今議論されています。それだけこの税金の関心度が高い訳です。政府にも税務調査会があり、政府だから強いと思うが、そうじゃない。各党の税務調査会の方が強いんです。だから今回の103万の壁についても、恐らく呑む方針となっているのです。政府はもう過半数がないのでこういった要求も呑まないと予算案が通らない訳です。
今日一番学んで貰いたいのは法が変わる事による別表の変化です。別表というのは何か、それは申告書です。法人が納める税金の計算は、別表で計算をします。昔は一枚で良かったのですが、だんだんと進化して増えてきました。別表というのは一般企業の損益勘定に伴う、所謂費用から損金に変える手続きを指します。これもレジュメで、そのところが来たらもっと詳しく話しますが、例えば寄付金とか、交際費、これは会計上ではもちろん費用です。が、税務上は交際費の大半は損金に算入されません。これを損金不算入といい、PLにかかる計算をするのが別表4となる訳です。逆にBSにかかる計算をするのが別表5となります。代表的なものが減価償却費で、実際償却はやってもやらなくても会計上は構いません。減価償却費について、法律で決まった法定年数の範囲内であれば損金になりますが、期間を短くしたりすると出っ張りが出てきます。その分は損金不算入となる、そういうルールがある訳です。会計上は短い年数でも、やらなくても、どちらでも自由です。自由ですが、税務上では別表5により耐用年数分だけが損金となる訳です。別表8に配当金の益金不算入があり、こちらも法改正で変わってくるものだから一緒に覚えて頂きたい。この様に法によりどんどん変わっていくものだから別表は増えていった訳です。今現在、別表がどの位あるかというと、最低30種類以上あるので経理も税理士も覚えるのが大変です。会社では別表4や5に重きを置いて、取捨選択し申告書を使い、表の表書きとして総合的な纏めの表が別表1となった訳です。最低限、別表1と別表4と別表5程度のものは、小さな企業でも作らざるを得ないのです。
個人でも確定申告、言葉は皆さんご存知だと思いますが、法人ほどの別表はないですけど、色々な表があります。住宅ローンや保険など、特別控除みたいなものをやってもらう表など税務署に行くと、色々と教えて頂けます。それを踏まえて自分で確定申告する訳です。そこで皆さま方に言葉として覚えて頂きたいのが、申告納税制度です。日本の税金の一番の特徴です。申告納税制度は他の国でもそうでしょうが、税金を納める者が納める金額を計算して納税するのが大原則としてあります。申告の必要がある人で申告をしていなかった場合は、刑法上の罰則がついて回る、だからみんな決められたルールを守っています。サラリーマンでいうと会社の給与に対して源泉徴収というものが法律で決まっております。源泉とは名の通り、泉の源を指し、大本の給与から税を徴収する。これも日本の税務体制の特徴です。源泉徴収は一種の予定納税です。ですから、年末に正確に税金計算をし、最終的に差額分を調整します。これが年末調整です。年末調整というと皆さま方の方が詳しいかもしれませんが、今年子供が生まれた、今年家を建てたなどの際には税金をまけてくれるのが年末調整です。申告納税制度というように本来は一人一人が申告して納税しますが、サラリーマンである我々は会社が代わりに纏めてやってくれる訳です。ただし年収が2,000万円以上あったり、2箇所以上から収入がある方は別途、確定申告が必要となります。その他にも例えば医療費や寄付金の控除がある際にも確定申告が必要となります。寄付金なんかも認定されているところに寄付した際には申告する事で、戻ってくる事があります。
といったところで、話していく内に税金の根幹を為す言葉が沢山出てきました。当たり前の言葉という人もいるかも知れませんが、きちんと整理して、そういう言葉が今後どんどん出てきますので、是非一つずつ覚えて頂きたいなという風に思います。
以 上