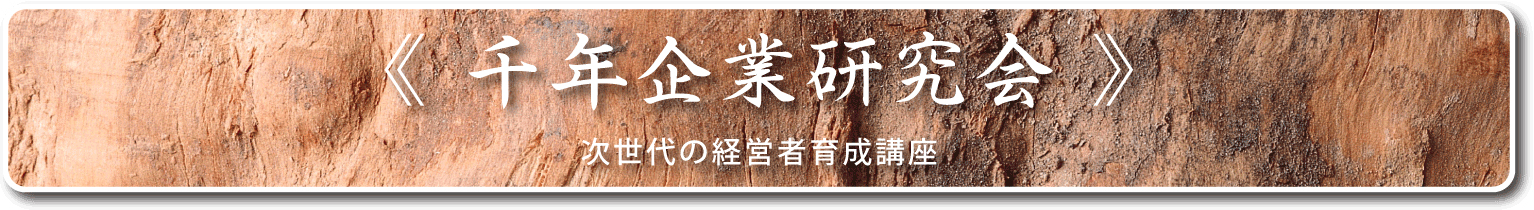
第135回 千年企業研究会(福井塾)議事録
令和7年1月29日
日本経済新聞の私の履歴書から
本日は先ず最初に日本経済新聞に掲載された「私の履歴書」から参考になった記事がありましたので、お話させて頂きたいと思います。
皆様ご存知の伊藤忠商事の岡藤さんという会長(現CEO)のお話です。この方の記事が今連載されているのですが、法人税に関する話があり、良い話だと思ったので皆様方にもお伝えしようと思います。
掻い摘んで説明すると、岡藤さんは東京大学を卒業後、伊藤忠商事に就職。最初の配属先は繊維部門でした。思い返してみると、彼の新入社員時代は社内でも評判になるほど生意気だったそうです。会社の方針として、配属して最初は事務を担当する訳ですが、とにかく生意気で仕事も失敗ばかりしていたそうです。同期もそうですが、通常2年位事務を担当したら、営業に出るそうです。やはり商社は営業が花形という事で、営業に出ると、自分は商社に就職したという実感が湧くそうです。ただ岡藤さんは、部長からお客様と喧嘩して会社の名を辱めたらとんでもない話だ、という事で「絶対営業なんか出させない。」と、後任の営業部長に申し送りされていたそうです。
暫くして、ある営業部長が岡藤さんを見て、何年経ったと聞くと、「4年経ちました。」と。「なんで営業に出てないんだ。」と事務方に聞くと、「営業には使わない方がいいですよ。」と。そこで営業部長はとにかく岡藤さんを観察したそうです。 そしてある時に事務方の責任者に岡藤さんを引き取ると伝えると、事務の責任者も「有難い、どうぞどうぞ。」と厄介払いみたいに追い出された訳です。
営業部長は「今日から営業に出させてやるが、1年間ある人を紹介するから、その人のセールスの仕方をとにかく全部学べ。」と伝えました。1年間はお客様とは勿論その人と一緒に帯同して、セールスの仕方を学ぶ訳ですが、年間はお客様の前でしゃべるな、とにかく只管メモしろと言われ、こんなに馬鹿にされた事はなかったので、6ヶ月も経たないうちに辞めてやると思ったそうです。また、その紹介されたセールスマンというのが同社の先輩営業マンじゃなく、下請け会社の営業マンという事でそこでもカチンときて、不貞腐れいい加減にやればいいと思ってやっていたそうです。
ただ、その営業マンがそれは物凄い人で、お客様に対する接し方や、セールストーク、それから何と言っても粘り腰が凄かったそうです。ある時はお客様に罵倒され、「もうお前の顔なんか見たくないから二度と来るな。」と言われても翌日には飄々と「こんにちは、今度はこういう繊維が出たんですよ。」って続けていく事で、お客様も「憎めない奴だな、それじゃあ一つ買ってみるか。」って商談が決まっちゃうそうです。その営業マンが一番得意にしていたのは、お客様のニーズを探る事で、そのニーズが判ると、それを一所懸命勉強して、そのニーズに応えてあげようとするから成績が上がる訳です。営業部長の1年間何にも言わずにメモだけ取れと言った事がよく解ったそうです。そうやってついて周ってる内に、こうすると売れるのか、セールスって面白いと思う様になり、ある日、本当に営業がしたくてしたくてしょうがないとなったそうです。
1年我慢して約束の日が来たら、営業部長に呼ばれて「よく我慢した。今日から一人前だ。」と営業に出られる様になりました。それから紆余曲折があって、自身でも色々体得した事を実践して、経験を積み実績を上げていった訳です。何に一番実績を上げたかというと、海外ブランドとの取引でバーバリーや、クロエ、エルメスといったブランドと次々と契約し、実績を上げてきた様です。ある時、仲間内で一杯飲んでる時に、海外ブランドもだいぶ開拓したけど、世界で一番のブランドはどこなんだろうという話になったそうです。いや、それはやっぱりジョルジオ・アルマーニが世界一のブランドで右に出るものはないとなったそうですが、当時の伊藤忠では相手にしてくれないと話していたそうです。そうしたら、たまたまそのアルマーニが日本支社を作った時だったそうで、これはチャンスだと。その日本支社の代表者を知っている人はいないかと、会社の先輩後輩同僚、取引企業あらゆるところにあたったそうです。そうしたらある時、アルマーニの代表と親しくしている人を知っている人が現れて、紹介してもらい接待しながらアルマーニの代表が今何に一番悩んで何を必要としているのかを探ってもらう様お願いしたそうです。その方は「月に1回位会うから、気が向いたら探ってみるよ。」といった具合で、暫くしたら「岡藤判ったぞと、あの人が望んでいる事は日本の税制だ。それも法人税制で、法人税制を学んで節税対策をやりたがっている。」と。探りを入れたらその辺りがニーズじゃないかという事で、岡藤さんは何日も徹夜で法人税を勉強したそうです。それで法人税が何かというポイントと、それを受けて日本の法人税制ではこういう事をやると節税になるよと説明する為に100ページにもわたるレポートを全部英文に訳して作り、ある日、約束を取り付けたそうです。日本支社の社長もそこまで熱心なら聞いてやろうという事でその場でペラペラと読んだそうです。そしてじっと岡藤さんの顔を見て、「判った。取引を始めてやるよ。」と三井物産だとか三菱商事といったところを出し抜いて契約をもぎ取ったそうです。岡藤さんが入社した時の伊藤忠は商社としては、4番手5番手とかで中堅どころの商社でした。ところが今やある部分では伊藤忠が一番だと言われる程の会社になった訳です。
ここまで話したのは、法人税というものは、社長のニーズの一つになるという事を、皆様方も社長になるからにはお伝えしたかったからです。社長になるなら法人税というものを勉強しておいた方がいいという事でこうした勉強会をやり始めた訳です。という事で、長くなりましたが早速本題に入って参ります。
継続企業の原則
レジュメに沿って進めていきますが、皆様には法人税を学ぶうえで計算方法を学んで頂きたいのではなく、考え方を学んで欲しいのです。基本原則について幾つか話していきますが、法人税とはどういったものかを考えながら聞いて頂ければと思います。
法人税の考え方としてゴーイングコンサーン、継続企業の原則と呼ばれるものがあります。企業が継続していくのは当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、企業が永続に続くという事とゴーイングコンサーンの考え方は違います。そこを話すうえで最初の株式会社、確かヨーロッパだったと記憶しています。どこかの港で船を作り、ヨーロッパの品々を積んで、東南アジアで売りつける。また現地の商品を船に積んで、帰ってきて、それをまた売る商売をしておりました。この1回転が終了し、会計報告をする流れです。何故報告をするかというと、船を作るうえでも商品を仕入れるうえでも貴族が多かった様ですが、出資者がおります。その1回転で設けたお金が幾らだったのかを報告して、儲けの中から分配し、出資した甲斐があった、となる訳です。ただし、当時の年数は1年を超え、2~3年だったそうです。今の1年単位というのは便宜的に作られたもので、2年3年で漸く利益を確保できる事業もあることから1年で切るのではなく継続していくことが重要となった訳です。
繰越欠損制度
継続して事業を続けるうえで、皆さまに覚えて頂いたのが繰越欠損制度です。欠損を繰越出来る名前の通りですが、中小企業の場合は、その期が赤字だった場合、その赤字欠損金を10年間累積出来る制度となっております。そしで、たまたま次の年に黒字になった場合、黒字額に応じて税金を払わないといけない、例えば黒字が1億円あったと仮定し、掛ける事の実効税率40%で4,000万円税金払いなさいとなった場合に、10億円繰越欠損があれば無税となる訳です。ここで、何故そこまで優遇してくれるのかを疑問も思わないといけません。先程の最初の会社でもそうですが、1年で区切ってしまってもまだ船の上で払えるものはありません。ですが、2年3年経つと莫大な利益を生みだし、そこから税金を徴収出来る様になる訳です。そうやって待つ事で得られるものがあるから繰越欠損制度を作ってまで企業を継続させる事に意味が出るのです。ただ、注意しなきゃいけないのは大企業の場合は2分の1しか認められていないという事です。これで繰越欠損制度は終わりですが、そもそもなぜこういう成り立ちをしているのかを考える事が大事です。
繰越還付制度
次に覚えて頂きたいのが繰還付制度、これがどういうものか皆さんご存知だと思いますが、例を出すと1年で1億円の黒字だったから3,000万円の税金を払いました。次の期は5,000万円の赤字を出したとすると、累積して2年で5,000万円の黒字となります。5,000万円に対して実効税率30%だったとしたら1,500万円となりますが、前期に3,000万円を支払っている事から差引1,500万円は還付しますといった内容です。
この制度は企業継続性の原則が元となっている考え方で、これは資本金1億円以下の中小企業だけに適用されます。大企業は摘要されず、期間も1年限りとなる点は留意してください。
本日はここで一区切りとさせて頂き、次回からは法人擬制説について説明していきます。これは二重課税、二重課税配当金の説明も入る訳ですが、配当金で受けたものについては法人では益金不算入という制度が適用出来ます。個人であれば税額控除となるのですが、こういった事を含めた言葉を皆様には覚えて頂ければと思います。
本講義ではデフォルメして話している部分も多々ありますので、自分自身で、頭に入れた事を根本的な理由は何なんだろうかという事に立ち返って、調べたりして考え方を身につけてください。
以 上